神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」 開催
佐野学園
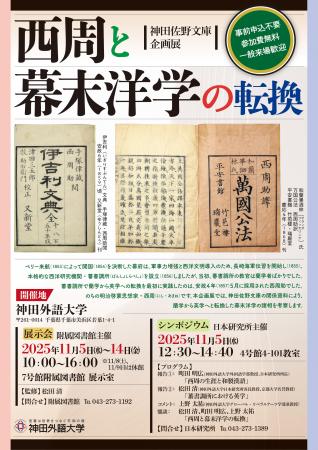
神田外語大学(千葉市美浜区/学長:宮内孝久)附属図書館は、2025年11月5日(水)から14日(金)にかけて、神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」を開催します。本展では、幕末の本格的な西洋研究機関・蕃書調所において、蘭学から英学への転換を最初に実践した西周の足跡を、神田佐野文庫に収められた貴重資料とともに紹介します。幕末から明治へと続く洋学の大きな変化を、資料を通じて考察します。また11月5日(水)には神田外語大学外国語学部教授・日本研究所所長の町田明広、本展示を監修した本学日本研究所客員教授・京都大学名誉教授の松田清、さらにグローバル・リベラルアーツ学部准教授の上野太祐によるシンポジウムを開催します。
〈展示会〉
[表1:
https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/196_1_d179ca6c74cddbe97ff0fbb6e4d64505.jpg?v=202510170516 ]
初日の11月5日(水)には日本研究所主催のシンポジウムを開催します。
本シンポジウムでは、西周の生涯や思想を通して幕末の洋学の展開を多角的に捉え、展示内容と連動した発表が行われます。
〈シンポジウム〉
[表2:
https://prtimes.jp/data/corp/78115/table/196_2_db03dc6b254ea3a8401dcf245985a36f.jpg?v=202510170516 ]
明治時代の啓蒙思想家・哲学者として名高い西周(にし・あまね、1829∼1897)は、文久2年(1862)オランダ留学に出発。ライデン大学フィッセリング教授のもとで、政治学・経済学・法学および哲学を学び、ホフマン教授編『大学 和字旁訓』刊行に協力しました。慶応元年(1865)帰国後、開成所教授ついで徳川慶喜側近となり、フィッセリング口述の『万国公法』(国際法)を翻訳しました(のち明治元年刊)。
明治維新後、沼津兵学校初代校長を経て、新政府の陸軍省参謀局に属し、兵語辞典編纂、軍人勅諭起草などを手がけました。この間、『百一新論』(明治7年3月刊)において、「ヒロソヒー」の訳語「哲学」を創出し、論理学の入門書『致知啓蒙』を出版(明治7年7月)。また、『明六雑誌』において、「洋字をもって国語を書するの論」を発表するなど、啓蒙的論文を次々に発表しました。
西周助(明治2年に西周と改名)は津和野藩医の子に生まれ、4歳で父から『孝経』、6歳で祖父から四書(『大学』『論語』『孟子』『中庸』)の素読を受け、20歳で藩校養老館句読(儒学助教)となりました。嘉永6年(1853)、25歳の時、ペリー来航に際し、藩から江戸に派遣されましたが、オランダ語を学び兵書を読むために脱藩。安政2年(1855)、蘭学者手塚律蔵の塾に入り、蘭書『ヘンチーヤンチー』(問答体理科入門書)を読破。翌年、手塚の命により、アメリカ帰りの中浜万次郎から英語の発音を学び、手塚所蔵のホルトロップ『英蘭辞書』をたよりに英書を読みました。
安政4年(1857)5月、幕府の洋学研究機関・蕃書調所に教授手伝並(講師)として採用され、並みいる蘭学者の中で最初に、英語文献の翻訳に取り組みました。万延元年(1860)の幕府遣米使節の際、米国留学を希望しましたが果たせず、文久2年(1862)、同年の同僚津田真一郎(のち真道)とともに、オランダ留学の命を受けることができました。
本展示では、西周が英学の開拓者として果たした大きな役割に注目し、神田佐野文庫所蔵の貴重資料32点を通して、蘭学から英学への転換期における洋学の諸相を考察します。
本学附属図書館神田佐野文庫は江戸時代後期から明治維新を経て、連合国軍占領期まで(1780年代から1950年代)の約170年間に、日本で刊行あるいは書写された西欧語・西欧文化の教育研究資料、および同時期に西欧世界で出版された日本関係洋書を幅広く収集した特色ある神田外語大学の文化交流史資料コレクションです。※ポスター別添
【町田明広】
哲学者、啓蒙思想家として知られる西周は、幕末維新期にも幕府留学生としてオランダで学び、帰国後は最後の将軍・徳川慶喜の側近として、『議題草案』を起草するなど、徳川による日本の近代化を夢想しました。また、西は東洋にはなかった西洋の様々な概念を持ち込むために、多くの和製漢語を作り上げ、現代でも日本のみならず、中国でも使用されています。西の生涯を、幕末期を中心に俯瞰するとともに、西による和製漢語の実相を知っていただくための、またとない機会となります。
【上野太祐】
西周は、日本が近代化に向かった最初期の思想家として近年注目されています。これまでは、翻訳語の成立、森鴎外『西周伝』と実際の生涯、宋学や徂徠学の思想的影響、熊沢蕃山への傾倒、東アジアの儒教近代化の中での位置、実証主義と「哲学」、軍事思想などが研究されてきました。そうした中、本シンポジウムは、西を「英学」の観点から捉え直す画期的な試みです。
[画像1:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/78115/196/78115-196-ca6e560778d15525d0d3508c8485785e-235x325.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



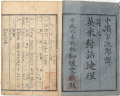
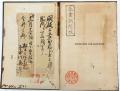
記事提供:PRTimes
![]()