製造業データ活用実態調査 ー進化する生成AI、停滞する社内DXー AI活用者の約8割が自社のデータに分断・不足等の支障を実感
キャディ株式会社

製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:加藤 勇志郎)は、製造業で働く200名を対象に「製造業データ活用実態調査」を実施しました。
[画像1:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-1293404e2dcf7b11bc7715a15e1625ec-1200x630.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
経済産業省が2018年に提起した「2025年の崖」。その年が、いよいよ終盤に差しかかろうとしています。しかし製造業の現場では、長年使い続けられている業務システムや属人化した業務が今なお残り、DXの停滞が根深く続いています。
一方、ビジネスパーソン個人のあいだでは、生成AIをはじめとするデジタル技術の活用が、この1~2年で急速に広がりました。
この「企業レベルの停滞」と「個人レベルの進化」というギャップは、製造業で働く個人のDXやデータ活用に対する意識にどのような変化をもたらしたのでしょうか。
本調査では、「個人ではAIを活用しているが、長年使い続けられている自社システムが残っている」と回答した200名を対象とし、個人のAI活用が組織に与える心理的影響や、データ活用の障壁、キャリア面でのリスク認識を明らかにしました。
■ 調査サマリー
・生成AIを使用している人の約6割(61.5%)は2024年7月以降から使い始めています。この1年ほどで個人のAI活用が急速に浸透していることがわかります。
・生成AIを使用している人のうち56.5%が「この1年間で生成AIの『進歩が非常に早いと感じている』」と回答し、「やや早く進歩している」も合わせると90.5%に達しました。AI技術の進化を体感している層が圧倒的多数であることが明らかになりました。
・自ら生成AIツールを活用するようになって以降、約8割(77.0%)が自社の長年使い続けているシステムについて「非効率・時代遅れだと感じるようになった」「より強く感じるようになった」と回答。AIの進化が自社システムの課題を顕在化させる契機になっている実態が浮き彫りになりました。
・とくに「AI技術が非常に早く進歩している」と感じている人ほど、自社の長年使い続けているシステムへの非効率感が強くなっていることが明らかになりました(「AIの進化を強く感じている」を選択した人の84.1%が自社の長年使い続けているシステムに非効率感を感じていると回答)。AI活用に積極的な層ほど、自社システムとのギャップに強く課題感を抱いていることが示されました。
・自社の長年使い続けているシステムが残っていることで「社内のデータ活用に何らかの弊害が出ている」と回答した人は85.0%に達しました。中でも「システム間で必要なデータが分断されており統合的に活用できない」(50.0%)、「ノウハウがデジタル化されず知見の再活用が難しい」(48.0%)といったデータの断絶や非構造化が主な障害として挙げられています。
・データ活用の弊害を放置することによる中長期的なリスクとしては、「ベテラン社員の退職・異動でノウハウがブラックボックス化する」(53.0%)が最多で、次いで「競合と比べて開発スピードやコスト競争力が劣る」(42.0%)、「属人化したノウハウが改善されず標準化・生産性向上が進まない」(36.0%)といった将来の競争力低下への懸念が挙がりました。
・長年使い続けている自社システムがDX化の妨げとなっている実態として、「DXを推進できる人材が不足している」(27.5%)、「既存システムやデータが複雑で整理・活用が難しい」(23.0%)が主要因として挙げられました。自社主導でのDX推進が難しく、外部パートナーとの協業が必要とされる傾向が見られます。
・所属企業でDXが進んでいないことによる個人への影響については、「生成AIやデジタルツールを業務に活かしにくく限界を感じる」(26.5%)、「新しいスキルや知識を学ぶ機会が制限される」(21.5%)、「他社や同僚と比べてスキルアップが遅れる」(20.0%)といったキャリア成長機会の損失が懸念されていました。
■ 調査結果
● 生成AIの利用、約6割(61.5%)が「2024年7月以降から使い始めた」と回答。この1年で個人レベルでのAI活用が急速に浸透している実態が明らかになりました。
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-99e1932ea5c4546a701085710dbdaca2-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
● 生成AI利用者の約9割(90.5%)が、「この1年間で生成AI技術の進歩が速い」と実感しており、機能や使いやすさの向上に対する肌感覚が広がっていることがわかりました。
[画像3:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-fde1bc60087aa22d3cee7f9175f64f4a-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
● 生成AIを使うようになったことで、約8割が自社の長年使われ続けているシステムを「より非効率・時代遅れ」と感じるようになったと回答。
[画像4:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-b1bf49d62e0aecd4f3fc0ae89708d9c7-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
● AIの進化を実感している人ほど、長年使われ続けている社内システムの「非効率」「時代遅れ」をより強く感じていることが明らかになりました。個人の技術体験が、企業のDX遅れを“より鮮明に認識させる”構造が浮かび上がっています。(クロス集計結果)
[画像5:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-44519bb6cddc05b38c79ed78adaf892f-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
・ここ1年間で個人でAIを活用する人が急増する中、特に技術進化を実感している層では、自社システムの「非効率」や「時代遅れ」をより強く認識している実態が浮かび上がりました。
・以前は漠然と感じていた非効率さが、AIによる圧倒的な業務効率化との比較によって「体感値」となり、課題として明確化されていると考えられます。
● データ活用に支障を感じている人は85%にのぼり、中でも「データの分断(50.0%)」「ノウハウの非活用(48.0%)」「デジタル化の不足(43.5%)」が課題として浮かび上がっています。
[画像6:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-d86458216940a040574ae679afaa1434-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
・長年使い続けているシステムが残ることによるデータ活用の弊害として、最も多かったのは「データの分断(50.0%)」。次いで「ノウハウの非活用(48.0%)」「データの非デジタル化(43.5%)」が続きました。これらは、製造業が抱える「技能継承の難しさ」や「知見の属人化」といった構造的課題を自社システムが温存していることを示唆しています。
・「特に弊害を感じていない」と回答した人はわずか15.0%にとどまり、多くの現場で長年使い続けているシステムが“データ活用のボトルネック”になっていることが明らかになりました。
● データ活用の停滞が、中長期的には「ノウハウのブラックボックス化(53.0%)」「競争力の低下(42.0%)」といったリスクを引き起こすと、多くの回答者が認識していることが明らかになりました。
[画像7:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-07e28aa59dc00c5d309a68103d2cd0ee-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
・回答の最多は「ベテラン社員の退職・異動により、特定の業務やノウハウがブラックボックス化する(53.0%)」。次いで「競合他社と比較して、開発スピードやコスト競争力が劣る(42.0%)」、「属人化されたノウハウが改善されず、生産性や業務標準化が進まない(36.0%)」が続きました。
・「優秀な人材が“この会社では成長できない”と感じて離職する(25.0%)」といった人材面でのリスクを挙げる声も多く、DXを担うべき人材のモチベーション低下や流出につながる可能性が示唆されました。
● 所属企業のDXが進まない理由として、「推進人材の不足(27.5%)」と「既存システムの複雑性(23.0%)」が主なボトルネックとして挙げられました。現場の課題認識に対して、解決を担う体制や技術的整備が追いついていない実態が明らかになりました。
[画像8:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-1ea9a9802bfc7ce7285765b06acdb165-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
・所属企業がDX化できていない理由として最も多く挙げられたのは「DX推進を担える人材不足(27.5%)」、続いて「既存システムやデータが複雑で整理が困難(23.0%)」という回答でした。
・DXを進めたいという意識はあっても、「人がいない」「技術的に難しい」といった壁が立ちはだかる実態が明らかになりました。こうした現場では、企業の状況に寄り添いながら進行を支援する“伴走型ベンダー”の存在が、DX実現のカギを握るといえそうです。
● 所属企業でのDX未整備が、「スキル習得の限界」「成長できない実感」などキャリアへの影響を及ぼしていると答えた人は8割超にのぼりました。
[画像9:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-3d223923b837352067da90544aaa6c9d-1920x1080.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
・最も多かったのは「新しいデジタルツールやAIを業務に活かしにくく、限界を感じる(26.5%)」、続いて「学ぶ機会が制限される(21.5%)」、「他社と比べてスキルアップが遅れる(20.0%)」と続きました。
・「特に影響はない(11.0%)」「問題はない(7.0%)」と回答した人はごく少数にとどまり、多くの従業員が「DXの遅れは個人の成長機会を奪う」と実感していることが明らかになりました。
<解説>
生成AIなどの技術に日常的に触れている個人がいる一方で、企業全体のDXは、依然として長年使い続けているシステムや人材不足といった課題を抱えたまま停滞している実態があります。今回の調査では、そうした“個人と企業のDXギャップ”が、現場の成長実感やキャリア形成にまで影響を及ぼしていることが明らかになりました。
特に、AIの進化を体感している人ほど、社内の長年使い続けている仕組みに「非効率」や「時代遅れ」を強く感じており、技術の進歩を知ることで、組織の課題がより鮮明に認識される構造が浮かび上がっています。また、データ活用の遅れは「ノウハウのブラックボックス化」や「競争力の低下」といったリスクを招くだけでなく、従業員のスキルアップや成長機会を阻む要因にもなり得ることが見えてきました。
DXの推進には、テクノロジーだけでなく、それを活かす人材と変革を支える仕組みが不可欠です。しかし、多くの企業では「推進を担う人材不足」や「既存システムの複雑さ」によって、変革が進めにくいという現実があります。そのため、課題の可視化にとどまらず、「どう変えていくか」を共に考え、現場の実行フェーズまで寄り添えるパートナーの存在が、製造業のDXを進める鍵になるといえます。
個人の意識が先行する今だからこそ、企業側も変化を受け止め、内外の知見を活かしながら、持続可能な変革へと舵を切ることが求められています。
===調査概要===================================
調査名称: あなたのお仕事についてのアンケート
調査期間:2025年10月3日(金)~ 10月8日(水)
調査方法:インターネット調査
調査対象者:製造業従事者
有効回答数:スクリーニング調査 6,000名、本調査 200名
表記:四捨五入し、小数第1位までの値で記載
※調査データの引用をご希望される際は、“キャディ調べ”と明記いただき、弊社までご一報いただけますと幸いです。
==========================================
[画像10:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/39886/169/39886-169-722e668dcce7479be5e4e8bfc243a3bd-1458x500.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]キャディ株式会社
キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計エクイティ資金調達額は257.3億円。
プレスリリース提供:PR TIMES

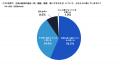



記事提供:PRTimes
![]()