【そのAIの回答信じて大丈夫? 】AIの嘘に騙されている人は約半数だった
株式会社AIスキル
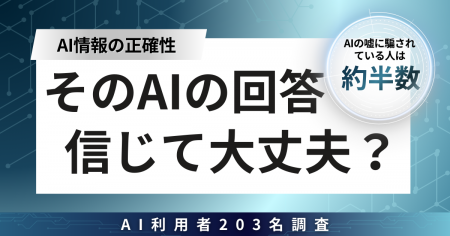
「情報収集」での失敗が最多。AIの嘘で7割以上が“余計に時間を浪費”する一方、デキる人は「検索」と「出典要求」で見抜いていた。
[画像1:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-ac3bbf6193663a568bbb90c94cecac1f-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
生成AIが業務に急速に浸透する中、その「情報の正確性」が新たな課題となっています。
5万人以上が受講した「最新AI活用セミナー」を提供するAIスキルアカデミー(運営:株式会社AIスキル)は、業務で生成AIを利用するビジネスパーソン203名を対象に、「AI情報の正確性に関する実態調査」を実施しました。
その結果、AI利用者のうち「AIの嘘を経験した」と明確に認識している人は55.7%に留まりました。
一方で、AIの嘘を経験した人の7割以上が「確認作業で余計な時間がかかった」と回答しており、AIを使いこなすには「嘘を見抜くスキル」が不可欠であることが判明。
本リリースでは、AIの嘘に「気づける人」と「気づけない人」の間に生まれつつある“リテラシー格差”と、本当の意味でAIを使いこなすためのコツについて解説します。
【調査サマリー】
- AI利用者の55.7%が「AIの嘘」を経験。気づかないまま利用する“無自覚リスク”も。- 嘘が多発する業務、圧倒的1位は「情報収集」。AI検索は注意が必要。- AIで時短のはずが…72.8%が「間違い修正で余計な時間がかかった」と回答。- デキる人の確認術は「Google検索での裏付け」と「AIへの出典要求」。
AIを業務で利用する203名に聞いた「AI情報の事実確認」の実態
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-78b0aefff7d4c30eff527d9c7b0e6812-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
本調査では、業務で生成AIを利用する全国のビジネスパーソン203名から回答を得ました。
年齢層は30代(39.4%)と40代(25.6%)が合わせて65%を占め、性別も男性(50.7%)、女性(48.3%)とほぼ均等であり、働き盛りの中核層がAIを活用している実態がうかがえます。
[画像3:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-3189952f638ce6a544532867b2e903b2-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
また、職種は「会社員(事務・総合職・専門職など)」(計65.6%)が過半数を占めつつ、「自営業・フリーランス」(23.2%)も2割を超えるなど、幅広い職務でAIが使われています。
注目すべきは、AIの利用頻度です。「ほぼ毎日(38.4%)」と「週に2~3回(31.5%)」を合わせ、約7割(69.9%)が週に複数回利用するヘビーユーザーでした。
ここからは、AIを日常的に使いこなしているはずの彼らでさえ直面している、「AIの嘘」の実態について、データを見ていきましょう。
あなたは気づける? AI利用者の約半数は見逃している「AIの嘘」
業務でAIを利用する203名に対し、「AIが生成した情報が事実と異なっていた(=AIに嘘をつかれた)経験」を聞いたところ、「ある」と回答した人は55.7%(113名)でした。
[画像4:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-8c059e2fd140fd856d8605a23bfa4bf0-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
AI利用者の過半数がAIの嘘を明確に認識している一方で、「ない」「わからない」と回答した44.3%の人々は、AIの嘘に気づかず、誤った情報を鵜呑みにして業務を進めている“無自覚リスク”にさらされている可能性があることが分かりました。
また、“AIの嘘を経験したことでAIへの信頼度がどう変化したか”という問いに対し、23.2%の人が、「むしろ、特性が理解できて使いやすくなった(23.2%)」という回答。
この結果から、AIの嘘に気づき特性を知ることが、情報リテラシー向上に繋がっているといえます。
AIの「それらしい嘘」によって起きた業務トラブル
では、AIの嘘はどのような場面で発生しているのでしょうか。
嘘を経験した人(N=116)に聞いたところ、「情報収集時(55.2%)」が他の回答を大きく引き離して1位となりました。
[画像5:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-d9b71273dc33c69aedfa4866f87c382b-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
AIを“万能な検索エンジン”のように過信して使うことにはリスクが伴います。
本調査の自由回答では、AIがいかに「それらしい嘘」をつくのかがわかる、具体的な業務トラブル事例が集まりました。
<業務で発生したトラブル事例>
- 市場調査レポートを作成中、AIにもっともらしい統計データを提示されたが、出典元を確認したら全く存在しないデータだった。- 法律上問題がないかを確認しようと尋ねたところ、e-Gov(イーガブ)※ にも存在しない法律を作られて、それに基づいて回答された。- ある分野の書籍を探していたら、実際には出版されていない本を捏造したり、雑誌の一部を本として紹介されたりして、事実確認に手間取った。- 介護福祉の研修資料を作成する際、実際には存在しない制度名や古い法改正前の内容が含まれていた。
※デジタル庁が運営するポータルサイトで、行政手続きや電子申請、法令検索などができます
時短のつもりが“逆効果”に。AIの嘘がもたらす本当の実害
[画像6:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-c7a6ccd30fab2ee86388bd023ab62b38-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
“AIの嘘から生まれたトラブルはあったか?”と質問したところ、「大きな実害はなかったが、確認作業に余計な時間がかかった(72.8%)」との回答が最多となりました。
致命的なトラブル(謝罪:2.6%)に至るケースは稀なものの、実に7割以上のビジネスパーソンが、AI回答の裏付けを取るために“逆に時間を浪費している”という実態が明らかになっています。
では、なぜ利用者はAIを鵜呑みにしてしまうのでしょうか。
アンケートでは「とにかく時間を短縮したいから(46.8%)」「自分の知らない専門分野だったので、正しいと思い込んでしまったから(45.8%)」の2つの理由が突出しており、“時短への焦り”と、“専門外知識への依存”という、2大心理が潜んでいることがわかりました。
デキる人はどう見抜く? AI時代の「情報の裏付けテクニック」
AIの嘘を見抜くために、デキる人はどのように対策しているのでしょうか。
AI回答の事実確認を行う方法を(N=203)聞いたところ、従来型のスキルと新時代のスキルを併用している実態が明らかになりました。
[画像7:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/158927/7/158927-7-11a064b80414eb2300d5eac06c40682d-1200x630.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
最も多かったのは「重要なキーワードで、従来通り検索エンジンでも調べる(67.5%)」でした。
AIを導入した後も、従来の検索スキル(=Google検索での裏付け)が依然として最も重要な確認手段であることがわかります。
続いて2位には「情報の『出典元』や『ソース』を具体的に尋ねる(55.2%)」がランクイン。これは、AIの特性を理解した上で、AI自身に証拠を提示させるという新時代のスキルです。
この結果から、AIを使いこなす人(=デキる人)は、AIの回答を鵜呑みにするのではなく、「検索」という従来のリテラシーと、「出典要求」という新たなリテラシーを組み合わせて、情報の信頼性を高めていることがわかります。
【まとめ】AI時代に必要なのは「使うスキル」と「見抜くスキル」
今回の調査で、業務でAIを使う人の過半数(55.7%)が「AIの嘘」を認識している一方、44.3%の人はそのリスクに気づかないまま業務利用している可能性が浮かび上がりました。
AIの嘘は「情報収集」で多発し、時短目的で使ったはずが、逆に「確認作業」で時間を浪費させています。
AI時代のビジネスパーソンに最も重要になるスキルとして、「AIに的確な指示を出すスキル(プロンプトスキル)(72.4%)」と「AIの回答の真偽を見抜くスキル(批判的思考力)(70.4%)」がほぼ同率でトップ2となりました。
AIは「正しい答え」を出すツールではなく、「それらしい答え」を生成するツールです。
これからのAI時代に業務の生産性を上げるためには、AIを便利に「使うスキル」と、その嘘を「見抜くスキル」をバランス良く習得することが必須となるでしょう。
本調査内容を掲載いただく際は、「引用元:AIスキルアカデミー」 の明記と、以下ページへのリンク設置をお願いいたします。
引用元:AIスキルアカデミー
https://ai-skill.jp/
■調査概要
調査概要:「AI情報の正確性に関する実態調査」
調査方法:インターネット調査
調査期間:2025年10月20日~31日
有効回答数:業務で生成AIを利用するビジネスパーソン 203名
■AIスキルアカデミーについて
AIスキルアカデミーは、「学ばない人が確実に取り残される時代」において、全てのビジネスパーソンがAIを武器にできるよう、実践的なスキル習得を支援します。5万人以上が受講したAIスキルアカデミーの「ゼロから始めるChatGPT活用セミナー」では、わずか2.5時間で明日から仕事で使えるAI活用スキルを一気に習得することが可能です。
AIスキルアカデミーの詳細はこちら
■会社概要
会社名:株式会社AIスキル
URL:
https://ai-skill.co.jp/
事業内容:生成AI活用に関する研修、セミナーの企画・運営
■リリースに関するお問い合わせ
株式会社AIスキル
担当:小森
メールアドレス:info@ai-skill.jp
プレスリリース提供:PR TIMES





記事提供:PRTimes
![]()